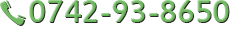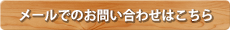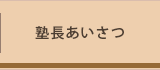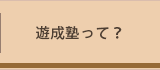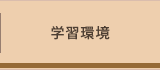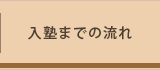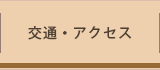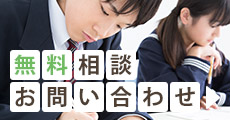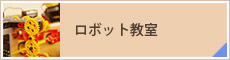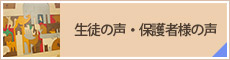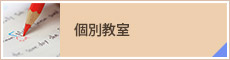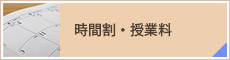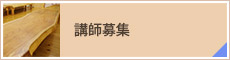カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年2月 (7)
- 2025年1月 (5)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (7)
- 2024年4月 (8)
- 2024年3月 (9)
- 2023年4月 (4)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (3)
- 2022年2月 (4)
- 2021年9月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2020年12月 (1)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (3)
- 2020年2月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年5月 (3)
最近のエントリー
遊成塾 Blog 8ページ目
算数でつまずくのはなぜ
特に中学受験の算数は難しく、「一所懸命にやっても全然できるようになりません」
といった悩みをよく聞きます。
算数でつまずく大きな原因は「公式」にあります。
公式の有用な点は、なぜかは分からなくても使えば求めたい値が出るということです。
たとえば、次のようなものです。
(底辺)×(高さ)÷2=(三角形の面積)
公式を知っていれば、どうしてこの式で三角形の面積が求まるのか
ということ自体を知る必要はありません。
当然、「なぜ?」と思って欲しい、理屈を知って欲しい、なるほどと思って欲しい。
けれども、この公式の場合、学習面において理屈を知らなくても支障を来たしません。
公式のメリットを考えると、上記の面積公式(円や扇形も含む)や、
小数や分数の四則演算(分数の割り算は割る数を逆数にして掛ける)、
最大公約数や最小公倍数を求めるためのすだれ算などはその利点を十分に生かせています。
理屈抜きで求められることで、より進んだ思考ができるようになります。
ところが、塾で教える公式(?)には有用性どころか、子どもたちを混乱に陥れるものがあります。
たとえば、次のような式に□があって、その値を求める問題(逆算といわれるもの)の公式です。
問題例) (8+□×2)÷6=3
公式例)□を求めるための公式
□+〇=△ → △-〇=□ | 〇+□=△ → △-〇=□
□-〇=△ → △+〇=□ | 〇-□=△ → 〇-△=□
□×〇=△ → △÷〇=□ | 〇×□=△ → △÷〇=□
□÷〇=△ → △×〇=□ | 〇÷□=△ → 〇÷△=□
これを見ると、子どもたちがなぜ算数ができなくなるのか、分かってもらえると思います。
ちなみに、大手進学塾のテキストには十中八九載っている公式です。
自分で考えて解かないといけない問題、ちょっと考えたら解ける問題を
こんな風にテキストの中で扱っていくわけです。酷いものです。
上記のような問題を見て、進学塾に通っている子どもたちは
「公式なんだったっけ、忘れちゃった!」って反応をします。
「公式なんて忘れちゃっても困らないから。今、自分で考えて!」と言って、
当塾では公式のことを気にさせない、公式を忘れさせる授業を行っています。
(遊成塾)
2017年2月27日 15:51





天神さんへの願い
早10日なってしまいましたが、改めまして
新年が無事明けまして、おめでとうございます。
我が家の初詣は毎年恒例の北野天満宮です。
人混み自体は好きにはなれませんが、
それとは異なり、賑わっているのを感じるのは悪くはありませんね。
参道に所狭しと並ぶ出店。
りんごあめ、わたがし、ベビーカステラ
からあげ、たこやき、ホルモン焼き
てきや、スマートボール、ヨーヨー釣り、くじ屋
往来で込み入る道を出店の様子を見ながらゆっくり通り抜けるのは楽しい気がします。
帰りには神社の詰所で受験生へのお守りを購入します。
人数に間違いがないか、何度も何度も生徒の顔を思い浮かべながら数えます(笑
どういう流れで妻とそんな話になったのかは忘れましたが、
初詣で北野天満宮に来て、どんなことを願っているのかという話題に。
もうかれこれ10年以上、天神さんには来ているような気がします。
願いはいつもと変わりません。
「子どもたちの努力のした分、結果が出ますように」
それと家内安全だけを毎年願っています。
受験はなかなか厳しいものです。
努力しなければ結果が伴わないのは当然ですし、それは仕方がないことです。
しかし、努力したのに結果に結びつかない、報われないということが往々にあります。
受からないというのは百発百中で当てられます。
けれども、受かるというのは当てられません。
理由は、この厳しさがあるからです。
勉強面だけではなく、精神面やいろいろなもの、性格までが影響を及ぼしてくるのです。
運による変な成功なんて必要ありません。
子どもたちにそんな経験はして欲しくないですし、自身もしたくありません。
けれども、努力した分の成功は得て欲しいですし、私も得たいです(笑
今週末、中学受験とセンター試験です。
当塾には中学受験生、高校受験生、大学受験生がおり、そこから受験が続いていきます。
努力した分の結果が出てくれればと思う次第です。
(遊成塾)
2017年1月10日 22:46





ラジオ番組に!
コメンテーターをしませんか
というお話をいただきました。
私自身、正直に言いますとラジオを聴いたことがほとんどありません。
(タクシーに乗ったときぐらいですか!?)
ですが、直接お会いまして話を伺い、出演してみることにしました!
妻にその話をすると
「何の話をするの?」
と…。いや、教育についてに決まってるでしょって答えると
「そりゃそうだよね」
と。
どんな話になるのか、細かいことは分かりませんが、
とりあえず「教育」について、お話をすることに。
5分ほどの番組ですが、面白く、元気が出る(?)お話になればと思っています。
先方に伺うのを忘れたので、奈良で聴けるのかどうか分かりません。(すみません)
お時間などの都合がよければ、是非聴いてもらえると嬉しいです。
調べてみるとスマートフォンのアプリで聴けそうでした!
(私はうまくできませんでしたが…)
ライブではないので、放送時間中も私は塾にいます。
そのへんはご心配なく。
////////////////////////////////////////////////////
放送局 :OBCラジオ大阪(AM ダイヤル1314KHz)
タイトル:ラジナビ(ラジオ・ナビゲーション)
放送曜日:木曜日
放送時間:PM 17:40~17:45(5分間)
放送期間:平成28年12月1日(木)から半年間
ナビゲーター:水野 潤子さん(アナウンサー)
////////////////////////////////////////////////////
(遊成塾)
2016年11月15日 16:37





山登り
奈良市内から車で1時間半ほどで葛城登山口です。
そこからロープウェイに乗ると6分ほどで山頂近くまで行けますが、
それではハイキングにもならないので、
ロープウェイ乗り場を横目に見て、登山道を登っていきます。
少し肌寒い日でしたが、天候には恵まれ、快晴です。
清々しい気持ちで登山スタートです。
登山コースとしては
櫛羅(くじら)の滝コース
北尾根コース
という2つのコースがあります。
北尾根コースは、山頂まで2時間ほどのコースで、
櫛羅の滝コースと比べると斜面が急で中級者向けらしいのですが、
その分(?)、景色は良いようです。
調べてみると最近(2009年頃)にできた新しいルートのようです。
櫛羅の滝コースは、1.5時間ほどのコースですが、階段が多いようで、
登山での階段は私はあまり好きではないので、
(誰も好きではないかもしれませんが…)
ちなみに登り口ではマップも頂けます。
詳細はマップに任せることにします。
*近鉄が作成している「てくてくまっぷ」というものです。(→サイト)
すごい数のマップがあります!
時間もたっぷりあり、帰りはロープウェイで下りてくれば良いと思い、
北尾根コースで山頂に向かうことにします。

しかし、登り始めると想像していたより遥かに急斜面が続きます。
山頂が959.7mという葛城山、きちんと考えれば当たり前といった感じの登山です。
小学2年生の娘は、上の息子とどんどん登っていってしまい、
視界からは早々にいなくなってしまいます。
年長の娘は、さすがにきついようでゆっくりゆっくり登っていきます。
かなり厳しい段差もあるので、そこだけは手助けをしますが、
基本的には自力で登らせます。
(意外とスパルタなのかもしれません)
時間をかけて登っていくと、一服できるベンチに到着。
上の子たちともそこで合流。
展望スポットのようで、景色は抜群です。

少し休憩をはさんで、また登っていきます。
急斜面が終わると、コース名通りの尾根伝いで
楽な行程になるに違いないと思いながら登っていきますが、
一向にそんな道にはならず、終わりのない急斜面が延々と続きます…。
園児は少し半泣きになりながら、それでも励まして、えっちらおっちら登らせていきます!
日和もよく、下りてくる方々もぼちぼち。
途中で達者な70代の男性と出会い、少しコースのお話を伺うと
途中で少し楽なコースを選べるとのこと。
このまま進むと階段700段ほどあるようで
(その方が数えられたようです!)
さすがに下の娘にはきつそうなので、そちらで向かうことに。
しかし、毎週(!)登ってらっしゃるようで、感服いたします。
怪我だけはされませんように。
急な登りをなんとか登り切ると、ようやく尾根伝いの路。

進んでいくと、おっしゃられたとおりの分岐点に到着。
そこで案の定、上の子たちも休憩していました。
「楽なコースは自然研究路の方らしいけど…」
というと、誰も何も言わずに進路をそちらに(笑)
楽だと言っても、それはあくまで比較の話なのでしょう。
そこそこ階段が続きます。

妻もさすがにきついと言いながら、がんばって登っていくと
スタートから2時間と少しでロープウェイの山上駅に到着!
ゴールだと思いきや、そこから山頂近くの白樺食堂まではさらに500mの登り坂。
さすがの上の娘もちょっと涙を浮かべてましたが、
あともう少しでお弁当だ
と励ましながら(?)最後の力を振り絞って登ります。
山頂は相当に寒いだろうと、着るものは持ってきていたものの、
油断したのは手のひらでした。
なにせ、手が寒い。
途中で缶ジュースのホットを買って、持たせながら、ようやくゴールです。
所要時間2時間30分ほど。
娘二人はがんばりました。
山頂でのんびりお弁当を食べて、ひと休みです。
自然の中で食べる手作り弁当は最高です。
朝早く起きて作ってくれた妻に感謝です。
子もども大人も、休憩を摂ると元気になります。
ただ、来た路を下りていこうとは言えず。
予定通り、ロープウェイで下りることに。
ロープウェイ乗り場からは絶景です。
(パノラマで撮れれば、本当に絶景がお伝えできたと思います!
そして、ロープが邪魔なのは、申し訳ない…)

2時間かけて登ったところを、5分少しで下ります。
子どもたちはどういう思いだったのかは分かりません。
もうかなり寒くなってきているのでこれからは難しいですが、
また春先になれば、気持ちよく登れることでしょう。
5月に咲く山頂のツヅジは有名なようです。
皆様、いかがでしょうか。
(遊成塾)
2016年11月 8日 16:39





秋の収穫
ちょうど時候もよく、暑くもなく寒くもなく。
ハロウィンというわけではないですが、いろいろな収穫を楽しんできました。
昼食のBBQも楽しくのんびりと過ごせました。
栗拾いは今年の最終日。
もうあまりよい栗は落ちていませんでしたが、娘たちは必至で探していました。
虫に喰われたものも多かったのですが、拾ったいくつかは無事だったようで。
しかし、二人揃って「栗は食べない」とか言うので驚きです。
ゆでた栗が嫌いな子どもなんていないだろうという偏見で、
食べさせて「おいしい!」と言わせないと!
と言っても、それは妻の役割ですが…。
どうやら、ケーキに入ったマロンとかが嫌いなようです。
その後、サツマイモ掘りもしました。
軍手をして、ひたすら掘るという作業ですが、子どもはこういうのが好きですね。
勢いよく掘って、芋に傷をつけていたので、慎重に掘るようにと!

掘ると色々な虫が出てきます。
アリやらクモやらハンミョウのような昆虫類やら。
別段嫌がることもなく、これは何だろうといいながら捕まえていました。
しかし、娘たちは収穫よりも虫取りの方が楽しいようで。
持っていった網を片手にずっと虫を追いかけていました。

経験があまりないので、なかなか捕まえられませんが…。
けれども、私が捕まえた虫たちを、平気で掴んで籠に入れていきます。
生き物に強く感心があるようで、見たり触ったりすることが楽しいようです。
私が子どもたちに見たり触ったりといった実体験をさせて満足している横で
妻がぼそっと言った一言に考えさせられました。
「一番楽しい収穫だけをできるっていいね」と。
なるほど、確かに。
妻の真意は分かりませんが、本当に「いいとこどり」です。
このような体験が悪いわけではないでしょうが、考えさせられる一言です。
答えとして合っているのかどうか分かりませんが、
庭に菜園を作ろう!
とか思った家路でした。
(遊成塾)
2016年10月11日 15:20





小学校 低学年はどんな勉強を
当然、その子に合わせて考えないといけませんが、
大切なことは楽しく行うことです。
どんな素晴らしいことをしても、勉強嫌いになってしまっては元も子もありません。
逆に言うと、楽しくしているのであれば、それがどんなことであれ、
子どもにとって価値があるものだと言えるでしょう。
小学校の低学年に限った話ではないでしょうが、
一言でいえば「楽しくしていること」が大切です。
「楽しく」取り組んでいるのであれば、
それが勉強であろうが遊びであろうが良いものとなります。
しかし、「遊びではちょっと…」と心配される親心も分かります。
そこで、今回おすすめするのがパズルです。
(パズルも遊びでしょうと言われると困りますが…)
パズルをしたからといって、急激に学力が伸びるわけではありません。
けれども、得られるものが多くあります。
まぁ、あまり打算的な話をしても、疲れるだけなので止めます。
パズルは年齢が低いほど純粋に楽しんでもらえて、
そしてそれゆえに得られるものが大きいと感じます。
ただ、小学生の低学年は大人用の脳トレパズルでは厳しい問題になってしまいます。
ほどよいと思うのは、宮本哲也さんの出している「賢くなるパズル」シリーズ(学研)です。
特に入門編、入門編2、基礎編、基礎編2は楽しく取り組めるものになっています。
使い方の詳細は、本に載っており、その通りでよいと思います。
当塾の生徒にも使っていますし、私の娘(小学2年生)にもさせていますが、
どの子も楽しく取り組んでいます。
楽しくない問題集を解くより、よっぽど健全で、そして価値があると思います。
よろしければどうぞ。
(遊成塾)
2016年9月 6日 16:09





祝 全国大会優勝!
おめでとうございます!
ロボット教室は難易度でコースが分かれており、
ベーシックコース、ミドルコース、アドバンスコースがあります。
普段の授業では、テキスト通りにロボットを作製し、
完成後にロボットの動きを観察し機構を学び、その後に改造をしていきます。
改造のお題は、その時のロボットと生徒の力に合わせて、出していきます。
「もっと速く進めるようにしてみよう」
「この図鑑の山を越えられるようにしてみよう」
「もっとゴミを集められるようにしてみよう」
「より長い時間、回っていられるようにしてみよう」
「まっすぐ移動できるようにしてみよう」
といった具合です。
この改造でも十分、創造力は養えますし、各生徒のオリジナリティがあり面白いものです。
ただ、毎年夏休みにある「ロボットアイデアコンテスト 全国大会」は改造とは異なり、
ゼロから自分でロボットを作り、そのアイデアを競う大会になっています。
もちろん、私自身もアドバイスはしますが、それは生徒の発想を広げるヒントのようなもので、
手伝うのはもちろん、生徒の創造を邪魔しないように心掛けています。
H君の創ったロボットは、ATMのロボットで、光センサーとギアの仕組みを上手く利用し、
正しいカードが挿入されれば紙幣が出てくるロボットでした。
誤ったカードを挿入しても紙幣は出てこないというもので、着眼点もよく、
それをロボットにしたアイデアも大変面白いものでした。
そして、見事、最優秀賞*(優勝)を勝ち取りました。
子どもが一所懸命に取り組む姿を見るのはとてもよいものです。
結果はともかく、その取り組み自体に価値があると思っています。
*最優秀賞は各コースそれぞれ1名ずつ、授賞します。
(遊成塾)
2016年8月29日 18:48





勉強で困らないで!
勉強はそれほど難しいものではありません。
正しく行えば、誰にでもできるものです。
難しいと思う問題でも、きちんと学べば、必ず理解できます。
そして理解したことを、忘れないうちに復習することで
必ずできるようになります。
小学生の内容はもちろんのこと、
中学校の内容も、高校の内容も、
大学受験の内容でさえ、そこまで難しくはありません。
大切なことは、
難しいと思ってあきらめず、
自分ならやればできると思い、
自身を持って、もう一度取り組むことです。
勉強は、誰でもやれば必ずできるようになるのです。
(遊成塾)
2016年8月11日 21:52





学び と 問い
『大学で「学ぶ」意味は』というタイトルで池上彰氏が書かれていたものです。
(2016/4/18 日経新聞(朝刊))
池上氏は「問いを立てること」だと述べられています。
私自身もそう思っています。
大学での「学び」は、それまでの学びとは大きく異なります。
小学校・中学校、高等学校では、子どもたちは「生徒」と呼ばれ、
「先生」に自明のものごとを教えてもらう場となっています。
「学ぶ」の語源と考えられている「まねぶ」「まねる」の言葉通り、
疑うことなく、教えてもらったことを取り入れていく作業です。
このこと自体が正しいことなのかどうかはさておき、現状はそのようになっています。
ところが、大学はそのような場ではありません。
大学生は「学生」と呼ばれます。
指導されている教授らは、当然人生の「師」、学問の「師」ですが、
どの学問も完全には確立されていません。
つまり、学問が未だ系統立てられていない、すっきりしていないというわけです。
このあやふやな点に対しては、「師」も「学生」も供に「考える」側として対等となります。
そういう意味では、大学での「学び」とは、今までの学びとは一線を画したものだと言えます。
ところで、「考える」という動作は、どのようにして行っていくのでしょうか。
考えようと思いさえすれば考えられるという単純なものではありません。
もっと考えなさいと言われて考えれるなら、誰も困っていないでしょう。
考えるために必要なもの、それが「問い」なのです。
「思考」は「問い」から始まります。
もっとも単純な問いは「なぜ?」「本当に?」というものです。
「なぜそうなの?」「本当に正しいの?」と問うことは学びの上で本来、とても大切なものです。
単純な「問い」から思考が始まり、思考する中で次のより的を射た「問い」が生まれます。
この繰り返しが思考だと私は捉えています。
「問い」は大学生になれば必要不可欠になりますが、
かといって、それ以前には必要のないものではけっしてありません。
「問い」を大切にすると必然的に時間は要してしまいます。
学びの効率を考えると回り道に思ってしまうかもしれません。
しかし、そもそも大学で教鞭を執っておられる池上氏がこのような話をされるのは、
偏差値の高い大学の学生でさえ、きちんと問いを立てられていないと感じられているからです。
氏はその原因を、受験教育における効率化だと言われています。
その通りだと感じます。
結局は、急がば回れになっているわけです。
幼稚園児から小学校低学年ぐらいまでは、当たり前のように行っていた問いかけです。
それをいかに大切にしていくかが今後の教育のポイントではないかと思います。
子どもたちが一所懸命考えてくれるためには、どのような問いかけがよいのか。
そんなことをよく考えるこのごろです。
(遊成塾)
2016年4月22日 16:37





英語って?
個別指導なので、小学1年生から高校3年生まで、
日頃の学習から受験指導、教科も一部を除いて大抵の教科を見ます。
その中で、やはり変わっているなと思う教科があります。国語と英語です。
数学、理科、社会は、学問として数学、自然科学、社会科学として、
きちんと成り立っているものの基礎という形で学んでいきます。
つまりは教養といったものでしょうか。
ところが、英語はそのようなものではありません。
どちらかというとスキルの類です。
つまり、泳ぎのスキル、釘を打つスキルといったものです。
英語を学ぶことで教養が身につくとは、とても考えられません。
(英文学を原書で読むとかなら教養になりますけど)
ただ使えるようになれば良いだけのスキルである英語が、
習得するのにどうしてこんなにハードルが高くなるのでしょうか。
私自身、英語では苦労をしました。
ものすごく遠回りをして、ようやく習得できたといったところです。
そして、思いました。
幾多の先人が英語を習得し、そのノウハウが蓄積されているにもかかわらず、
どうして習得への道が整備されていないのか。
子どもたちの英語の指導をしていて一番これを感じるのが学校の教科書の英語を扱っているときです。
製作に携わった方々に、是非伺いたいですね。
「ご自身が英語を習得するのに、この教科書があればよかったと思われたものを作っておられるのですか」
「この教科書で、英語は使えるようになるのでしょうか」
と。
子どもたちの置かれている環境、そして持っている悩みのことを考えると、
教科書英語を無視して授業をすることができません。
そして、そのために英語を習得するのに、生徒も先生も悪戦苦闘することになります。
事実、教科書英語の縛りから解放された高校3年生に英語の授業をすると、
驚くほどできるようになります。
伸び悩む生徒でさえ偏差値10ぐらいは軽くあがります。
調子がよければ+20とかも普通です。
あ、間違えないでください。
教科書英語で作った下地があるから、伸びているわけではありません。
実際に放っておいたら、酷いまま受験に突入ということになっています。
もちろん、英語なんて、ぱぱっと簡単に短時間で習得できると言っているのではありません。
英語を習得するのには膨大な時間が必要です。
努力も当然必要です。
ただ、手順を間違えずに行えば、かならず習得できます。
子どもたちには、その道さえ示してあげれば、あとは本人が努力するだけです。
それは、子どもたちにとって難しいものではありません。
どんなことでも、努力なしでできるようにはなれないということは、大抵の子どもたちは知っているからです。
努力してもその先にゴールが存在しない道や、そもそも道すら存在しないものを、
子どもたちに与えるのはやめてほしいですね。
子どもたちは、とても頭がよいです。
「先生、○○ってする意味ってあるんですか」
と聞いてきます。とても鋭いです。
私は正直に答えます。
「残念ながら、意味はないですね。なのでやめましょう。
代わりに、△△をしましょう。△△にはこういう理由で意味があります。」
と。
(遊成塾)
2016年3月10日 21:46