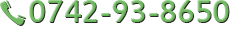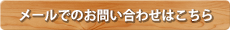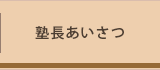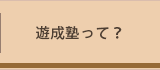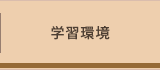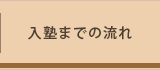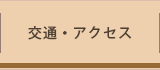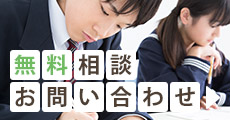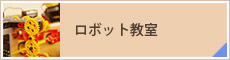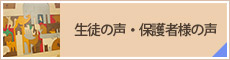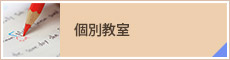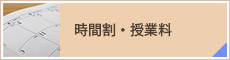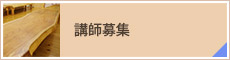カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2025年2月 (7)
- 2025年1月 (5)
- 2024年6月 (3)
- 2024年5月 (7)
- 2024年4月 (8)
- 2024年3月 (9)
- 2023年4月 (4)
- 2022年5月 (2)
- 2022年3月 (3)
- 2022年2月 (4)
- 2021年9月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (2)
- 2020年12月 (1)
- 2020年9月 (2)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (4)
- 2020年6月 (3)
- 2020年2月 (1)
- 2017年2月 (1)
- 2017年1月 (1)
- 2016年11月 (2)
- 2016年10月 (1)
- 2016年9月 (1)
- 2016年8月 (2)
- 2016年4月 (1)
- 2016年3月 (1)
- 2015年12月 (1)
- 2015年10月 (1)
- 2015年9月 (1)
- 2015年5月 (3)
最近のエントリー
遊成塾 Blog 5ページ目
「やる気」が出ないのは
- 生徒「勉強をやらないといけないことは分かっているんだけど、やる気が出てこないんです…」
- 保護者「うちの子、なんか勉強に対してのやる気がなくて…」
これはとても多い悩みの一つです。
世の中には「やる気スイッチ」みたいな言葉があって、そのスイッチを押すと、さも「やる気」が出てくるみたいな話があります。けれども、これはただの商売文句。
残念なことですが、「やる気スイッチ」みたいなものは存在しません。
Q.「やる気が出ない」という状況では、何をすればよいのでしょうか。
この答えを知るためには、まず「やる気が出ない」理由を知る必要があります。
その理由を知った上でどう解決をしていくのかを考えていけば、結果悪いことにはなりません。
やる気が出ない大きな理由は、確固たる目標がないことです。これについて、遊成オンライン学習のブログにて少し詳しく整理してみました。参考にしていただければ幸いです。
≫「やる気が出ない」本当の理由
(遊成塾)
2023年4月18日 16:09





問題が解けるためには
もしそれが分かると、問題が解けるようになる(かもしれません!)。
「問題を解く」プロセスは、簡単に整理してみると次のとおりです。
- 問題を読み、内容を把握する。
- 把握した問題が自分の知っている問題のどれに該当するかを吟味し、決定する。
- 該当すると考えた問題の解き方に沿って解いていき、答えを求める。
このことを遊成オンライン学習のブログで少し丁寧に説明してみました。是非参考にして成績アップに役立てて頂けたら幸いです。
≫【勉強法】問題を解けるようにするために必要なこと2つ
(遊成塾)
2023年4月 7日 14:00





浪人が成功するかどうか
浪人自体は決して悪いものではなく、就職活動時においても人生においてもネガティブな要素にはなり得ません。
今の時代にはほとんど見受けられませんが、私が受験した1990年代やそれ以前は「第一志望は〇〇大学、第二志望は駿台!」とか言っていた時代でした。「どうしてももう一度チャレンジしたい!」と思えば浪人するのは大いにアリです。
ただ、浪人すれば第一志望に受かるのかといえば、それは別の話。実は思っているよりもはるかに厳しい世界になっています。これは次の事実が物語っています。
- 浪人して成績が上がるのは20~30%
- 第一志望校に合格するのは数%
≫浪人が成功するかは、スタート時点でほぼ決まります
(遊成塾)
2023年4月 5日 14:57





成績を上げる方法
学習塾で指導している側からすると成績を上げることだけが目的ではないのですが、できれば成績は上がって欲しいものです。
そこで成績を上げるのに必要なことを整理してみました。
成績を上げるのに必要不可欠なことは3つです。
- 想い
- 勉強時間
- 戦略
ただ、かなり良い成績を修めたいといった場合はきちんとした戦略が必要かもしれませんが、平均点+αくらいならば大切なのは強い想いと勉強時間の確保です。
これなくして成績は上がりません。塾に通うだけではダメですし、「上がればいいなぁ」といった他力本願的なものもアウトです。
何か得たいものがあるならば、それを得るために自身で努力する必要があります。
詳しくは遊成オンライン学習のブログに載せておきました。
よかったら一読ください!
≫成績を上げる方法
(遊成塾)
2022年5月13日 16:57





学習塾ってどういうところ?
上手くなりたいと思って練習していく中で、直した方が良いことや正しい練習の仕方などを教えてくれ、成功に導いてくれるのがコーチです。
塾も同じで、一生けん命に勉強している中で、「こういう風に勉強したら上手くいくよ」「この点は直した方がいいよ」というアドバイスを提供してくれるのが学習塾です。
✓明確な目標がある場合
明確な目標があり、それに対して努力を惜しまずがんばりたいと考えているならば、塾でアドバイスを受けつつ勉強していくのはアリでしょう。
思考錯誤しながらさまざまな努力をしたけど、結局ダメでしたというのは絶対に避けたいところです。それを避けるために必要な情報を提供してもらえる塾を利用するのは一つの手だと言えるわけです。
✓努力の割に結果が伴わない場合
もし、努力している割に結果が伴っていないと感じるならば、自分の現状を解決するために必要な手助けやフォローを塾に求めるのも良いでしょう。
自分で解決の糸口を苦しみながら探すよりは断然楽になれるはずです。もし現在通っている塾で上手くいっていないと思うならば、思い切って塾を変えることも大切かもしれません。
現状を変えたいならば、何かしら変えないと、良くも悪くも変化は起きないですからね。
それに成功への道は1本道ではありません。一つの道にこだわること自体は悪いわけではありませんが、上手くいかないと思うならば自分に合った道を探すことも大切です。
(遊成塾)
2022年5月12日 16:34





「板書を写す」という行為
ノート提出の課題がある場合は当然写すほかないのですが、実は「板書を写す」こと自体にメリットはありません。
(正しくいうと、板書自体は復習時に必要だったりしますが、写すという行為自体に意味がありません)
信じられないかもしれませんが、次の2つの事実を知ると考え方は変わると思います。
- 板書を写しているとき、先生の話は聞けていません
- 板書で写した内容は全く覚えていません
詳しくは遊成オンライン学習のブログを参考ください。
≫【授業】板書を写すときに気を付けたいこと
https://yusei-online.com/blog/copy-board-writing
(遊成塾)
2022年3月19日 16:00





思考力を鍛える
「思考力を鍛えたい」
最近よく耳にする「思考力」という言葉。
実は、少し勘違いしているところがあります。
それは、「思考力」とは「考える力」のことではないということです。
たしかに思考力という言葉の意味は考える力のことです。
けれども、世間で使われている「思考力」という言葉はそれを意味していないのです。
全何回になるかは分かりませんが、遊成オンライン学習内のブログにて、
「思考力を鍛える」ということをテーマに数回に渡って整理をしています。
よければ一読していただければ幸いです。
≫【思考力を鍛える#1】思考に必要なのは4つの能力
https://yusei-online.com/blog/how-to-train-thinking-power1
≫【思考力を鍛える#2】情報を把握する力
https://yusei-online.com/blog/how-to-train-thinking-power2
≫【思考力を鍛える#3】情報を把握する力(算数編)
https://yusei-online.com/blog/how-to-train-thinking-power3
≫【思考力を鍛える#3】情報を把握する力(数学編)
https://yusei-online.com/blog/how-to-train-thinking-power4
(遊成塾)
2022年3月10日 16:26





暗記力がない?
「暗記は苦手」
よく聞くフレーズですが、この言葉に私が返す言葉は、
「暗記力に個人差はないですよ!」
というものです。
暗記力には個人差があって、
暗記ができている人は、暗記力があるから楽にできている
暗記ができない人は、暗記力がないからできない
と思っているようですが、実はそれは単なる被害妄想。
暗記ができている人は、暗記するために膨大な時間をかけているのです。
よければこちらも読んでもらえたらと思います。
≫【暗記】暗記ができないのはなぜだろう
https://yusei-online.com/blog/why-cant-you-memorize
(遊成塾)
2022年3月 1日 21:48





大切なのは英文法!
英単語の暗記、英語の長文読解
これは、多くの受験生がそう思っていて、
放っておくとこの2つの勉強をし続けることになります。
でも、残念ながら、この2つはいくらやっても英語ができるようにはなりません。
正しい勉強は
英文法
なのです!
詳しくは遊成オンライン学習のブログにて。
≫【英語】英語の文法、大切にしていますか
https://yusei-online.com/blog/do-you-value-english-grammar
(遊成塾)
2022年2月28日 21:42





数学の勉強法
簡単に言うと、次のとおりです。
- 教科書傍用問題集で、公式の暗記と簡単な使用法を理解する。
- 受験参考書(基礎)で、入試で必須の考え方を理解し、解法パターンを暗記する。
- 入試問題集で、入試の頻出問題の解き方を理解し、きちんと解けるようにする。
- 過去問(赤本)で、実践的な演習をする。
≫【数学】大学受験に向けて用いる問題集と勉強法(前編)
https://yusei-online.com/blog/how-to-study-math-for-entrance-exam1
≫【数学】大学受験に向けて用いる問題集と勉強法(後編)
https://yusei-online.com/blog/how-to-study-math-for-entrance-exam2
(遊成塾)
2022年2月24日 21:34